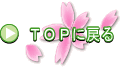|
子どものころ海やプールへ行くと、僕は一人で底に沈み、水中から水面?を眺めることが大好きだった。
いったいどういうことかと言うと、まず水面に仰向けに浮かび、ゆっくりと息を吐いていく。 体の中の空気が徐々に抜け、自分の体重が浮力に勝ったとき、体はそのままの状態で沈み始める。
底から見る水面が、しだいに遠ざかる様子は結構楽しい。
耳を済ませば、水中にもさまざまな音が漂っているし、何より、徹底した孤独感がいい。
だけど体の中の空気は残り少ないので、その楽しみも長くは続かず、きつい状況になってくる。
泳ぎが達者でないと、いつものような浮力の助けは少ないので、かなり危険な遊びだったと言えよう。
こんな話をすることには理由がある。
人間は母親の体から生まれ出たとき、はじめて呼吸し、それが産声となる。
そのときはじめて吸い込んだ空気が、人間の体の中には死ぬまで残っていて、だから人は故郷に戻ると、その体内の空気と同調することになり「やすらぎ」を感じる、そんな話しを聞いた。
この考えはなかなか詩的で、故郷を愛するものにとっていつでも故郷を抱いているような気がして、なんだかありがたい気になる。
僕はその体内に宿る空気とは、僕が子どものころに水の底で感じていた、残りわずかの空気のことではないか、そう思うのだ。
水中という、いわばぎりぎりの状態の中、僕は自分の心臓の音を聴きながら、体内にわずかに残された空気が、僕の誕生につながっていることを無意識のうちに感じていたのかもしれない。
もしも自分の中に、生まれてはじめて吸った空気がずっと残っているのなら、その空気は僕の体験とともに在るということだ。
僕が言葉や、歌声を発するとき、他人の音を感じるとき、僕は僕につながるそのわずかな空気を充分に振動させたい。
たまには余計な空気を吐き出して…
|